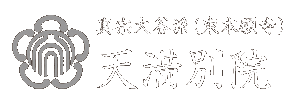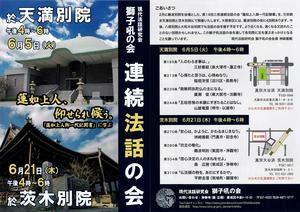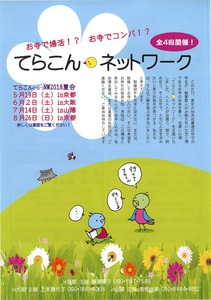五月 同朋の会 開催報告
天満別院では、五月十三日(日)の十四時より同朋の会が開催されました。
前回に引き続き、『正信偈』に出てくる天親菩薩について大阪教区第七組 長教寺住職 稲垣 洋信師よりお話をいただきました。様々なことをお話していただきましたが、中でも「遊煩惱林現神通」に書かれている煩惱という言葉から、人間にはいくつ煩惱があるのか。諸説には、四苦(4×9=36)、八苦(8×9=72)を合わせた百八個とも言われており、その四苦八苦は、生老病死という根本的な四つの苦に加え、求不得苦、怨憎会苦、愛別離苦、五蘊盛苦の四つを合わせて八苦ということを教わりました。
この日は朝から雨が強く、普段と比べると参拝者も少なかったですが、次回は三ヶ月ぶりに座談会を予定しております。また皆様お誘い合わせのうえ、ご参拝くださいますようご案内申し上げます。