天満別院 機関紙「六字城 」八月号
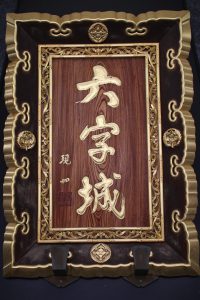
天満別院では昭和38年8月の創刊より毎月機関紙「六字城」を発行しております。
先日645号(平成30年8月号)を皆様にご郵送させていただきました。
また天満別院ホームページにも公開いたしました。
下記リンクからも閲覧できるようになっております。
皆さま是非ご覧くださいませ。

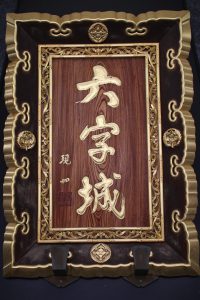
天満別院では昭和38年8月の創刊より毎月機関紙「六字城」を発行しております。
先日645号(平成30年8月号)を皆様にご郵送させていただきました。
また天満別院ホームページにも公開いたしました。
下記リンクからも閲覧できるようになっております。
皆さま是非ご覧くださいませ。

八月四日(土)の午後五時から天満別院にて天満別院 教化委員会 法要部会主催の崇敬寺院対象の報恩講習礼を行います。
今回の内容は「巡讃 内陣 出退の習礼及び心得」です。
崇敬寺院の方で得度式を受けておられれば、どなたでもご参加できます。
今回ご持参いただくものは大谷派声明集(東本願寺出版)、大谷派声明集(下)、真宗の儀式(声明作法)、裳附、五条、差貫、間衣、輪袈裟です。
※五時御始の際には、裳附、五条、差貫、装束着用お願いいたします。
参加をご希望の方は、天満別院までお電話ください。
電話番号は06−6351−3535です。
天満別院では、七月十二日(木)に天満別院教化委員会 法要部会主催による報恩講習礼を開催致しました。
第一回目の習礼は「正信偈(句切)の習礼及び心得」についてでした。
初めての正信偈(句切)にみなさん慣れないもの法要部の先生たちと一緒に元気よく読まれていました。
次回は八月四日(土)の午後五時より、「巡讃・内陣 出退の習礼及び心得」について開催致します。
ご持参いただくものは真宗大谷派声明集(上・下)真宗の儀式、間衣、輪袈裟、裳附、五条、差貫となっております。なお習礼開始の五時の時点で装束を付けた状態でお待ちくださいますようお願い申し上げます。
参加をご希望の方は、天満別院までお気軽にお電話ください。
電話 06-6351-3535 FAX 06-6351-3547
天満別院では、七月八日(日)の十四時より同朋の会が開催されました。
前回に引き続き、『正信偈』に出てくる天親菩薩について大阪教区第七組 敎應寺住職 建部 智宏師よりお話をいただきました。前回、前々回も天親菩薩についての内容でしたが、今回は正信偈の書き下し文から内容を考えていくものでした。「天 親 菩 薩 造 論 説」は天親菩薩が『仏説無量寿経』の影響を受けて『浄土論』を書かれましたとお話されました。また、本願寺派の寺族の方も来られまして様々な角度から議論や説明が出ました。
今日は久しぶりの晴れた青空になり気持ちいいほどの快晴でした。来月は諸般の事情により同朋の会はお休みいたしますのでよろしくお願いいたします。
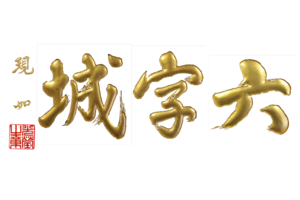
天満別院では昭和38年8月の創刊より毎月機関紙「六字城」を発行しております。
本日644号(平成30年7月号)を皆様にご郵送させていただきました。
またホームページにても公開いたしました。
下記リンクからも閲覧できるようになっております。
皆さま是非ご覧くださいませ。

二〇一八年七月一日(日)、天満別院において久世 信様・村上 真貴子様の結婚式を執り行いました。
ご結婚おめでとうございます。
別院では結婚式を随時受け付けております。寺院関係の方々だけでなく、ご門徒の方々の挙式もご遠慮なくお申し込みください。